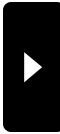2014年07月17日
第一幕の始まり始まり 【観察】
『やっちまった』 その後にも
まぁ~立ち直りは早いほー。
そんでもって『やっちまった partⅡ』も・・・・そこは触れずにスルー。
目的魚じゃないし。
ただサイズはこのぐらい。
(釣り人だったら両手をこのぐらいって広げてみよう)
蓄積するダメージ、溜まる、溜まる、溜まる・・・・
なので少しばかりの観察と言うリフレッシュタイムを頂くことに。
観察も釣りの一部ですから。
ビルの渓谷を走る川やら運河だと川面の観察よりも、
橋の下から見上げる先のおねぇさまの観察に勤しむことになりそうなところですが、ここは別世界。
初めての土地であり見るもの全て新鮮そのもの。
緑豊かな渓谷だと釣りをせずとものんびりと川面の様相を観察できるモンです。
よっこいしょと砂利玉地に腰掛け、周りをぐるりと一眺め。
関東平野の下流域、高低差がないぺターンとしたところで生まれ育った人間にはありえない景色。
今座っているここからすぐそこは河口が見え、そこからは水が塩辛くなる海が見える。
なのに真後ろには山、その先も山山山が連なって重なっているし。
その山の合間の谷の隙間を縫うように流れてくる川。
長さは短く高低差は激しく。
上流と下流しかない感じだろうか。
水色もありえないぐらいクリア。
茶色みがかった混じり物の泥がどこにも見られない。
沈殿する時間が無いのか、混じる込む泥が無いのか。
少しだけ白濁しているように見えるが、これが普通の水色なんだろうか。
この川はどんな川なんだ?と考え出す。
考え出すなら見てみるほーが早い。
でもって上流探索。昇れそうな所まで、行くぜ、上流!
(何かのキャッチコピーみたいだがオリジナルは俺である。すっげー昔から使っているし。)
想像したとおり川幅は太い!でも俺からしてみれば間違いなく渓流であり清流である。
約200Km遡れば同じような光景が関東でも見れる。
でもここは渓流と清流、それに川の終わりと海が約1/10の距離で見られる。
約20kmもない長さの中に上流・中流・下流がギュっと詰まっている。
(あくまでも上流・中流・下流の定義を無視して自分なりの解釈と見た目の独断と偏見で)
鱸ならアリだけど、ヤッコサンはここまで昇らん。
これが結果。
どんな流れ、どんな水温、どんな塩分濃度を好むかも知らないくせに、
なんとなく『ここは鱸!』と断言しちゃったし。
『夏になったらここっしょ』とまで言い切っちゃったし。
でもこの【カン】は大切だと思う。
まったく知らない土地に来て、右も左も分からない状況で何でもかんでもとできる日程でもない。
切り捨てることも大切である。
でも、でも・・・うぶな鱸がいっぱいいそうと、
よだれを垂らしながら後ろ髪を引かれながらその場を撤収しないといけない。
釣り人としてやっていいのか、この行為。
まぁ仕方ないので半ふてくされ状態で川を見ながら下る。
鱸ならあそこ。ブラックならここ。タイリクならここかなと。
ふてくされ状態もそんなことを考えているとニコヤカになっているのが不思議。
それでも最後は魚信があったところに戻ろか。だった。
夏になったらヒグラシを声を聞きながらここで釣りをしたいね。
ウェーダーを脱いで釣りをしたいね。
水を直接感じて釣りをしたいと思わせる川でした。

さてさて、戻ってこんどはお魚さんがどんな行動をするのか観察しましょう。
まだまだ続く、この釣行記。
(やけに引っ張る)
よろしければ、またのお越しを。
まぁ~立ち直りは早いほー。
そんでもって『やっちまった partⅡ』も・・・・そこは触れずにスルー。
目的魚じゃないし。
ただサイズはこのぐらい。
(釣り人だったら両手をこのぐらいって広げてみよう)
蓄積するダメージ、溜まる、溜まる、溜まる・・・・
なので少しばかりの観察と言うリフレッシュタイムを頂くことに。
観察も釣りの一部ですから。
ビルの渓谷を走る川やら運河だと川面の観察よりも、
橋の下から見上げる先のおねぇさまの観察に勤しむことになりそうなところですが、ここは別世界。
初めての土地であり見るもの全て新鮮そのもの。
緑豊かな渓谷だと釣りをせずとものんびりと川面の様相を観察できるモンです。
よっこいしょと砂利玉地に腰掛け、周りをぐるりと一眺め。
関東平野の下流域、高低差がないぺターンとしたところで生まれ育った人間にはありえない景色。
今座っているここからすぐそこは河口が見え、そこからは水が塩辛くなる海が見える。
なのに真後ろには山、その先も山山山が連なって重なっているし。
その山の合間の谷の隙間を縫うように流れてくる川。
長さは短く高低差は激しく。
上流と下流しかない感じだろうか。
水色もありえないぐらいクリア。
茶色みがかった混じり物の泥がどこにも見られない。
沈殿する時間が無いのか、混じる込む泥が無いのか。
少しだけ白濁しているように見えるが、これが普通の水色なんだろうか。
この川はどんな川なんだ?と考え出す。
考え出すなら見てみるほーが早い。
でもって上流探索。昇れそうな所まで、行くぜ、上流!
(何かのキャッチコピーみたいだがオリジナルは俺である。すっげー昔から使っているし。)
想像したとおり川幅は太い!でも俺からしてみれば間違いなく渓流であり清流である。
約200Km遡れば同じような光景が関東でも見れる。
でもここは渓流と清流、それに川の終わりと海が約1/10の距離で見られる。
約20kmもない長さの中に上流・中流・下流がギュっと詰まっている。
(あくまでも上流・中流・下流の定義を無視して自分なりの解釈と見た目の独断と偏見で)
鱸ならアリだけど、ヤッコサンはここまで昇らん。
これが結果。
どんな流れ、どんな水温、どんな塩分濃度を好むかも知らないくせに、
なんとなく『ここは鱸!』と断言しちゃったし。
『夏になったらここっしょ』とまで言い切っちゃったし。
でもこの【カン】は大切だと思う。
まったく知らない土地に来て、右も左も分からない状況で何でもかんでもとできる日程でもない。
切り捨てることも大切である。
でも、でも・・・うぶな鱸がいっぱいいそうと、
よだれを垂らしながら後ろ髪を引かれながらその場を撤収しないといけない。
釣り人としてやっていいのか、この行為。
まぁ仕方ないので半ふてくされ状態で川を見ながら下る。
鱸ならあそこ。ブラックならここ。タイリクならここかなと。
ふてくされ状態もそんなことを考えているとニコヤカになっているのが不思議。
それでも最後は魚信があったところに戻ろか。だった。
夏になったらヒグラシを声を聞きながらここで釣りをしたいね。
ウェーダーを脱いで釣りをしたいね。
水を直接感じて釣りをしたいと思わせる川でした。
さてさて、戻ってこんどはお魚さんがどんな行動をするのか観察しましょう。
まだまだ続く、この釣行記。
(やけに引っ張る)
よろしければ、またのお越しを。
Posted by ほら吹き男爵 at 07:17│Comments(0)
│固有種を求めて
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
|
|
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。 |